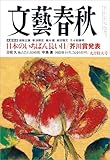2025年上半期は、芥川賞も直木賞も受賞作がないという、およそ28年ぶりの珍事が起きて話題になった。
いったいどんな議論の末に受賞作が決まったのか(あるいは今回のように受賞作なしに決まったのか)。その議論の様子や議事録は公開されないが、実はどのような議論があったのかは、選評を読むことで窺い知ることができる。
ご存じでない方も多いかもしれないが、芥川賞の選評は月刊誌『文藝春秋』に掲載されている。また芥川賞は小説家たちが選考委員を務めている賞であり、現在の選考委員は、小川洋子、奥泉光、川上弘美、川上未映子、島田雅彦、平野啓一郎、松浦寿輝、山田詠美、吉田修一の9名(50音順)である。
この記事では、2025年度上半期の芥川賞がなぜ該当作品なしになったのかを、選評の一部を読み解いていくことによって、紹介していきたいと思う。もっと興味のある方はぜひ、月刊『文藝春秋』2025年9月号を買って詳しい選評を読んでみてください。

2025年度上半期の芥川賞候補作
はじめに、今回の芥川賞の候補作を紹介したい。今回の候補作は以下の4作品であり、最近の傾向では5作品、時には6作品が候補作になっていたので、4作しか選ばれなかったのは少なかったといえるだろう。
グレゴリー・ケズナジャット『トラジェクトリー』(『文學界』6月号掲載)
駒田隼也『鳥の夢の場合』(『群像』6月号掲載)
向坂くじら『踊れ、愛より痛いほうへ』(『文藝』春号掲載)
日比野コレコ『たえまない光の足し算』(『文學界』6月号掲載)
ちなみに芥川賞の候補作は、その上半期・下半期に、文芸雑誌で発表された純文学作品が対象となる。
そのため、雑誌名を記した。また、芥川賞の候補作になるために、単行本が発売されている必要はない。
各選考委員は何を書いているのか
では、以上4作品について、9人の選考委員はどの作品が受賞に相応しいと考えていたのか、それとも受賞作なしが妥当だと考えていたのか、講評を読み解いていこう。なお、以下の作家順は『文藝春秋』の講評掲載の順番である(原稿が届いた順番に掲載されているらしい)。
松浦寿輝は『鳥の夢の場合』、『トラジェクトリー』の2作を推していた。
小川洋子は、「どの作品を推すか決められないまま臨んだ」と書いている。一方で『たえまない光の足し算』について、「評価を超越したエネルギーを放っていた」と書いており、この小説のもっと突き抜けてほしかった作品についても書いているのだが、高く評価しているようだ。
山田詠美は選評で「この賞の歴史を知らない人も多いみたいだから言っておきたいのだが、『受賞作なし』なんてざらにあること」と、受賞作なしの報がSNSを駆け巡った際に一部で起きた、選考委員への非難に対して応えるような文章を寄せている。「むしろ、芥川直木賞両方に受賞作が出ていたここ数年の方が珍しいのである。私や島田雅彦が候補になっていたころは、「受賞作なし」が続いたりもしたのだ(二人とも結局受賞していない)」とも書いている(ちなみに山田詠美は、結局直木賞をとっている)。受賞作なしで構わない、というスタンスだったのだろう。
最近の芥川賞はダブル受賞も頻発している印象があり、一度受賞基準の引き締めを図りたいというような意図が選考委員たちにあったのではないか、というような意見もSNS上では見られた。こういった意図があったのか、なかったのかは分からないが、候補作を受けて「今回は受賞作なしでいいのではないか」という意識は選考委員の中に当初からあったのかもしれない。
吉田修一は各小説の講評を書いているが、強いて言えば『トラジェクトリー』を最も高く評価していたようだ。
島田雅彦は、山田詠美も書いているように、島田雅彦は何度も芥川賞候補に選ばれるも結局受賞することができなかった。「一九八〇年代に六回候補になり、そのうち五回該当作なしだったという苦い経験を持つ私は当時の選評を恨みとともに覚えている」と、今回の選評でも書いており、やはり受賞作なしという結果になっても致し方ないという意識はあったのではないかと思われる。一方その中でも、『たえまない光の足し算』を「一押し」していた。
平野啓一郎は「受賞作が出なかったことは残念だが、いずれも、可能性に富んだ候補作であり、今後のキャリアを考えても、もう一段上の作品で、近い将来に受賞した方が良いと思う」と書いている。今回の候補作家は、いずれももっと代表作となるような小説を書けるはずであり、その時に受賞した方がよいという意見である。
奥泉光は、『鳥の夢の場合』と『たえまない光の足し算』が「好み」であったようだ。
川上弘美も各作品の講評を書いているが、どの作品を最も高く評価しているのかはよくわからない。
川上未映子は「今回は相対評価で『トラジェクトリー』のみ受賞の水準に達しているのではないかと思い選考に臨んだが、決戦投票で過半数の賛同を得られず、該当作品なしという結果になった」と書いている。
選評から導かれる結論
川上未映子の選評に端的に記されているように、今回の選考会議では『トラジェクトリー』を受賞させるかどうかが最終的な問題となったが、結局受賞作なしとすることになったというのがその経緯なのだろう。
『トラジェクトリー』という作品が受賞できなかった理由としては、複数の選考委員が書いているように、この作品が一作品で読者を満足させる作品というよりは「続編を期待させる作品」であったことだろう。
たとえば、島田雅彦は選評で以下のように書いている。
今回も思ったのは、ケズナジャット氏は、日本との屈折した関係、アメリカとの違和、異世界に生きる孤独を深く掘り下げり第二章、第三章を書くべきだということである。
また、今回、筆者が選評を読んでいて最もなるほどと思ったのは、先ほども引用した平野啓一郎が書いた以下の文章だった。
今後のキャリアを考えても、もう一段上の作品で、近い将来に受賞した方が良いと思う
『トラジェクトリー』は続きが気になる作品であり、選考委員としては、その続きが書かれた作品こそ芥川賞受賞に相応しいという思いがあったのだろう。
もし次に傑作が待ち受けているのであれば、作家としても、その作品で芥川賞という大きな賞を取る方がよいに違いない。受賞作なしは、選考委員の小説家としての親心なのかもしれないと思った。
おわりに
28年ぶりの芥川賞・直木賞どちらも受賞作品なしということで話題になった今回の芥川賞・直木賞だが、なぜ受賞作品なしになったのかは、選考委員が説明している。興味を持った方は、ぜひ選考委員の選評を読んで、候補作も読んでみてほしい。
そして、今後も芥川賞を注目してほしいと思う。
(ちなみに、月刊『文藝春秋』にはいつも芥川賞受賞作の全文が掲載されるのだが、今回は受賞作なしだったので「最も受賞に近かった作品」である『トラジェクトリー』が全文掲載されている。選評が読める上に、小説も読めてお得なので、興味のある方はぜひ読んでみてほしい)
◆この記事は◆現在の日本で最も話題になる文学賞である「芥川賞」「直木賞」と「本屋大賞」について、その違いをご紹介します!「芥川賞」「直木賞」と「本屋大賞」、耳にしたことがある方がほとんどだと思いますが、意外とこれらの賞の違い(特に芥川賞[…]
第164回芥川賞に輝いた『推し、燃ゆ』(おし、もゆ)を読んだ。結論から言うと、主人公にあまり共感は出来なかった。だが、主人公に共感できないというのは、小説が面白くないということではない。小説としては「推し」という現代的なテーマを純文[…]
安部公房は、日本で最もノーベル文学賞に近かった作家の一人であると言われる。それは安部公房が海外で高く評価されていたからであるが、現代の私が読んでみても、安部公房の作品は「海外文学的」である。もちろん安部公房の作品が生まれた土壌には渺[…]