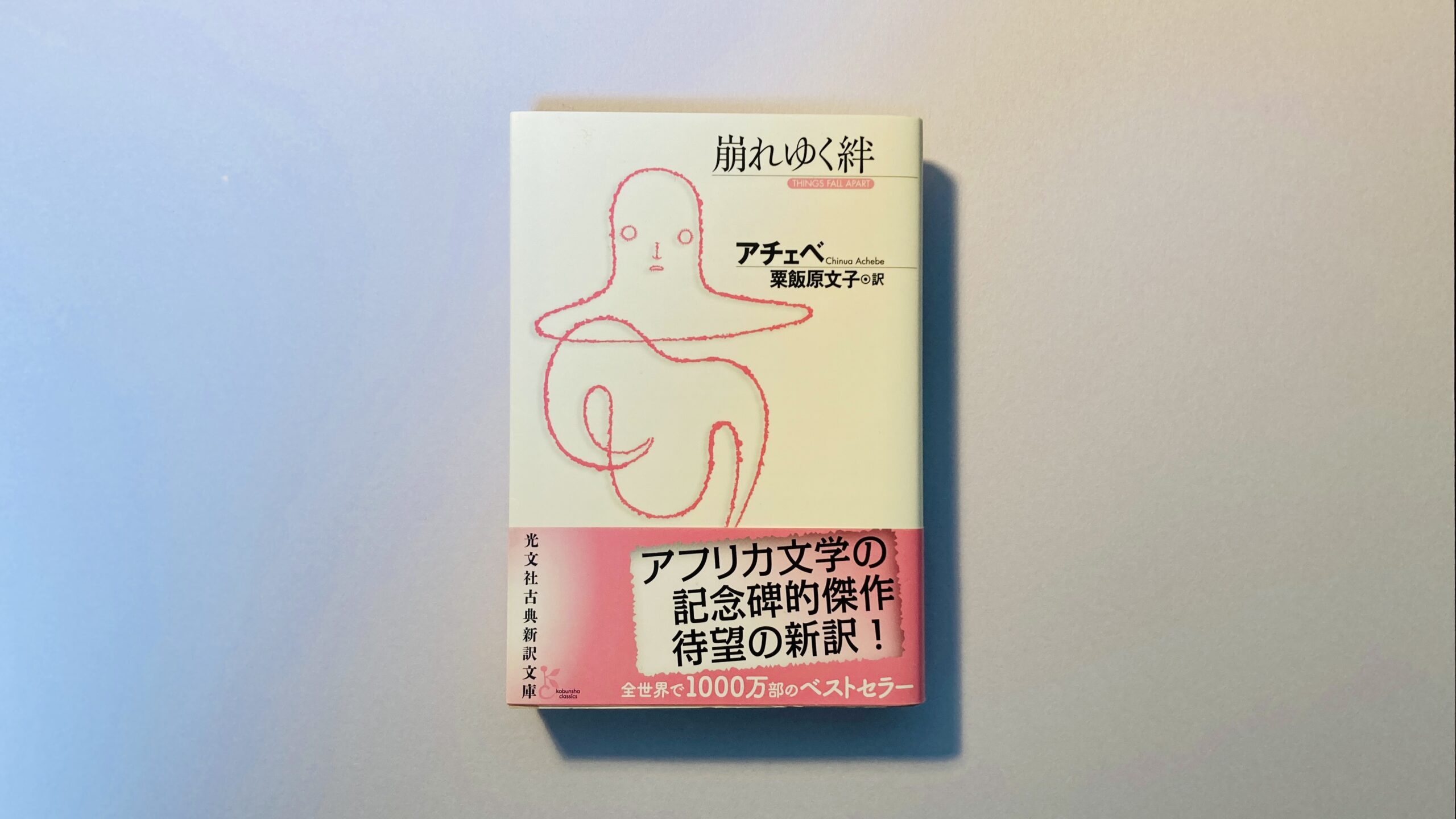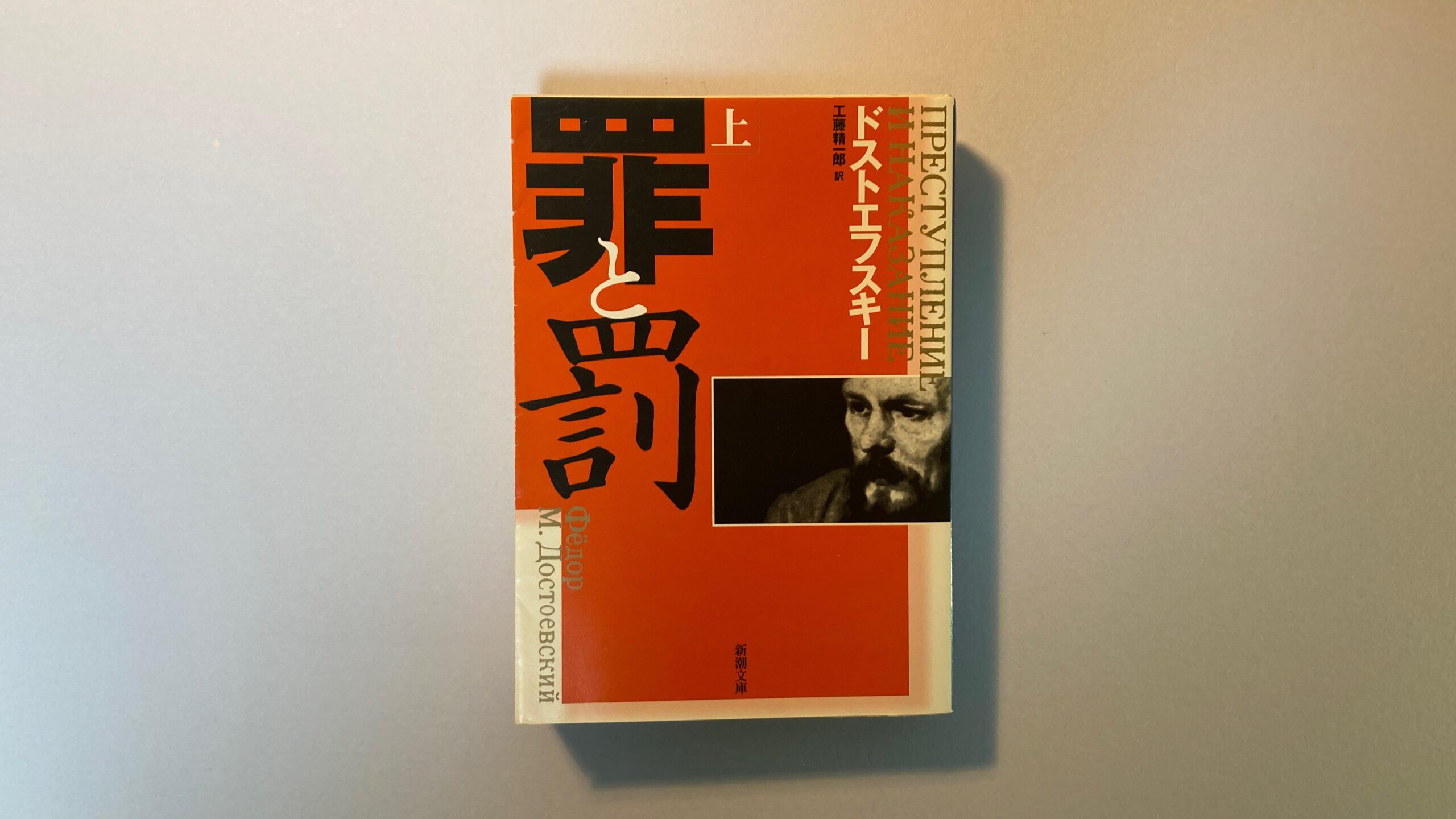あまりにも有名だが、ドストエフスキーは、かつて死刑囚であった。
若き日のドストエフスキーは、ペトラシェフスキーの主宰する社会主義サークルに所属し、皇帝(ツァーリ)の統治下にあって、社会の変革を目論んだために官憲に逮捕された。ペトラシェフスキーはじめ、ドストエフスキーらサークル員は死刑判決を受けたが、銃殺直前になって皇帝ニコライ2世から恩赦を与えられ、シベリアへの流刑に処せられたのである。
ドストエフスキーがこの時刑場の露と消えなかったのは、世界文学史上の幸いである。
(もっとも、官憲にはもともとドストエフスキーらを死刑にする気はなく、一連の死刑判決と恩赦は、彼らに死の恐怖を味わわせるために仕組まれた一種の拷問――英語で言うMock execution(模擬処刑)――であったのだが。)
人間・ドストエフスキーにとっては、死の恐怖を味わわされ、さらには流刑を体験することになったのは不幸なことであっただろう。史実として、ドストエフスキーは流刑時代に健康を悪化させている。
しかし、ドストエフスキーが死刑判決を受けて死の恐怖を味わい、またシベリアの刑務所で約五年間の服役を受けたことは、小説家・ドストエフスキーにとってはむしろ幸いだったのかもしれない。
ドストエフスキーが、不幸ではあるが得難く極限的な体験をしたことによって、ドストエフスキーの作品は他の作家にはない深みがあるのだから。
ドストエフスキーが刑期を終えてからしたことは、自らの刑務所での体験を書きあらわすことであった。この作品こそが『死の家の記録』である。
ドストエフスキーを文壇に復帰させたこの作品は、小説としては不完全な部分がある。だが、その不完全さは必ずしも作品の価値を損なっているわけではない。
この作品はあくまで小説であるから、ノンフィクションとして読むのは違うと言われるかもしれない。しかし、この作品の魅力は、小説の主人公の目を通してドストエフスキーが当時のシベリアの刑務所を克明に描写しているところである。
実際に囚人としてシベリアでの監獄生活を送ったドストエフスキーは、どのように世界を見て、どのような思考を巡らせたのか。その生々しい体験を読み取ることができるところに、『死の家の記録』という作品のたぐいまれなる価値があると私は思う。
『死の家の記録』あらすじ・概要
前置きである程度言いたいことは言ってしまったのだが、はじめに『死の家の記録』という作品の概要について紹介したい。
『死の家の記録』は、ある無名の語り手による序文から始まる。
遠いシベリアの果ての曠野や、山や、樵道もない森の中で、ひょっこり小さな町に出会うことがある。
そのような町に、アレクサンドル・ペトロ―ヴィチ・ゴリンチャコフという、流刑を終えた貴族がいた。彼は、かつて嫉妬に狂って自分の妻を手にかけ、懲役10年をシベリアで過ごしたのである。
殺人犯とはいえそれ以外の面では彼は品行方正であり、今は外界とのかかわりを極力避けながらも、地元の有力者の娘に家庭教師をして生活をしていた。
アレクサンドル・ペトローヴィチ・ゴリンチャコフが死ぬと、語り手は、彼が刑務所で残した手記を見ることになる……。
そして手記の体裁を取り、アレクサンドル・ペトローヴィチを主人公として、本編が始まるのである。
『死の家の記録』感想
アレクサンドル・ペトローヴィチは、監獄へと護送され、監獄への生活を送ることになる。
ここに、『死の家の記録』でアレクサンドル・ペトローヴィチが受けた監獄の「最初の印象」を紹介しよう。
監獄へ来て、わたしの第一印象は、全体として実にいやなものであった。ところが、それにもかかわらず――奇妙なことだが!――監獄の生活は、わたしが途々想像してきたよりも、はるかに楽なようが気がした。
囚人たちは、枷をはめられてはいるが、監獄内を自由に歩きまわり、にくまれ口をきいたり、歌をうたったり、自分の仕事をしたり、煙草をふかしたりというふうで、酒を飲むものさえいたし(もっともこれはごく一部の者だが)、中には毎晩博奕をやっている者までいた。
たとえば、労働そのものにしても、けっしてそれほど辛い苦役とは思われなかった。
そしてこの労働の辛さと、苦役であることの特徴が、労働が苦しく、絶え間ないものであるということよりは、むしろそれが強制された義務で、笞の下ではたらかなければならない、ということにあることをさとったのは、かなりあとになってからである。
これを読んでいただければわかるように、アレクサンドル・ペトローヴィチの収容された監獄は、意外にも生き生きしている空間だったのである。
獄吏も腐敗しており、また労役中に近隣住民と接触できるため、監獄の中には貨幣経済が成立している。酒も密輸されたり密造されたりしている。受刑者たちは娯楽のために口喧嘩をしたり、また受刑者たちは時に演劇もする。
私たちが現代の刑務所に対して抱くような印象とは、かなり違う。
そしてそこに生きる人々に対して、ドストエフスキーの透徹した視線が向けられるのである。
ドストエフスキーが描く犯罪者の形態は、おそらく現代の犯罪者の形態と重なるところが多いだろう。倫理観がずれていたり認識能力の低さゆえに犯罪を犯してしまう人間もいれば、ただ単に殺人を快楽と思うようなシリアルキラーもいる。あるいは(かつては善良な人間に見えていたのかもしれないが)自分が信じる目的のためには手段を選ばない、日本の元首相暗殺犯のような人間もいる……。そんな極悪人たちが、この作品には登場する。
ちなみに、アレクサンドル・ペトロ―ヴィチは貴族であることは、作中で非常に重要になる。貴族は、庶民とは身分からして違った。だから刑務所に入っても、アレクサンドル・ペトロ―ヴィチは貴族と見られているのである。そこに身分の差があり、それもこの作品のテーマとなる。
おわりに
以上が、『死の家の記録』の簡単な内容である。
はじめに『死の家の記録』は小説としては不完全であると書いた。それはなぜかというと、アレクサンドル・ペトロ―ヴィチがなぜ妻を殺したのか、最後になるまで語られないからである。『死の家の記録』は、監獄の描写がひたすら続いて終わる。
だが、私は『死の家の記録』は、はじめドストエフスキーは小説として書こうとしたものの、途中から実質的にノンフィクションとして描くことになったがゆえに、このような形の作品になったのではないかと思うのである。
また、昔から指摘されているように、『死の家の記録』で提示されたテーマは、のちの作品でテーマとなっている(たとえば、『カラマーゾフの兄弟』の父殺しなど)。だから、『死の家の記録』は、ドストエフスキーが体験した監獄の記録を描いたノンフィクション的な作品ということでいいのである。
もちろん読書には好みがあるので万人受けはしないだろうが、個人的には『死の家の記録』はかなりおすすめの一冊である。
ドストエフスキーの長編より前に書かれた作品であることに加え、(分厚いけれども)文庫一冊でドストエフスキー作品にしては短いこともあり、個人的には、ドストエフスキー作品の中で最初に読んでもいいのではないかもしれないと思う。
ちなみに私が参照したのは新潮文庫版だが、上の『死の家の記録』の光文社古典新薬文庫版は、Kindle Unlimitedという定額読み放題サービスで読めるので、こちらも合わせてお薦めしておきたい(初月無料、記事投稿日時点)。他にもいろいろな古典的名作を読むことができるサービスである(このサービスで読める本については本ブログのKindle Unlimitedカテゴリをご参照いただきたい)。
KindleはスマホやPCのアプリでも読むことができるので、体験したことがない方は一度試してみてはいかがだろうか。