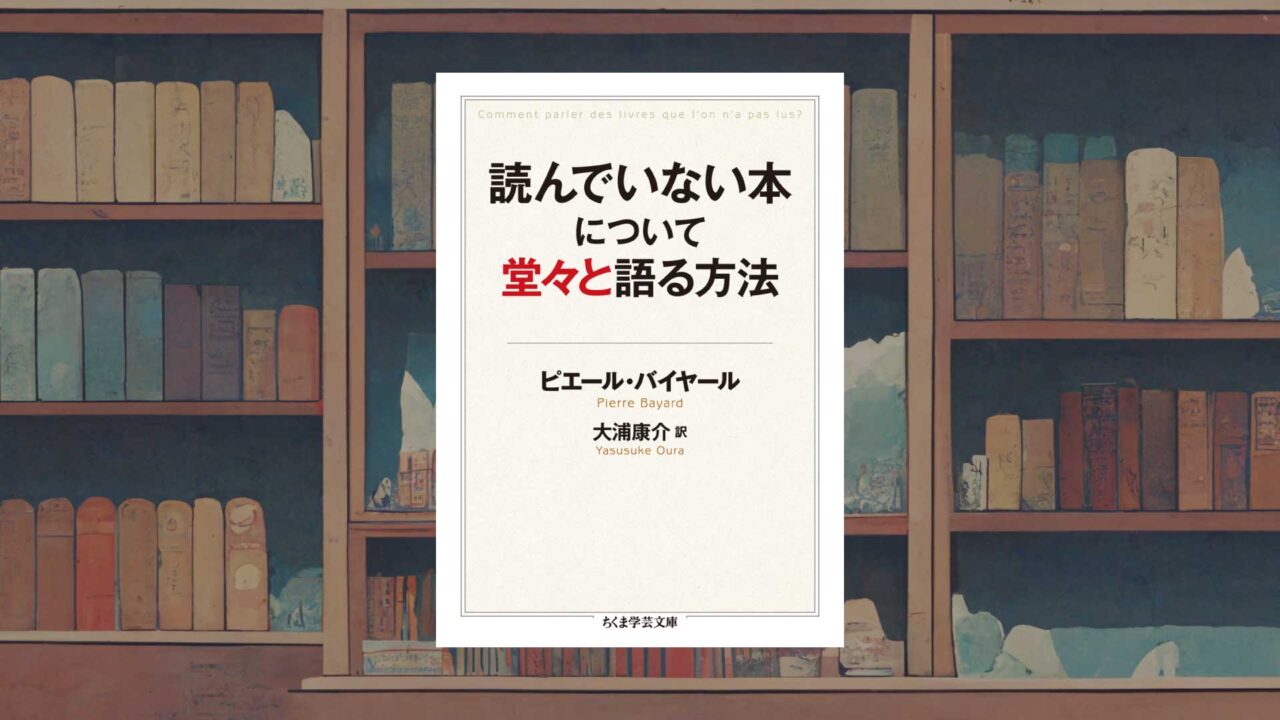ピエール・バイヤール『読んでいない本について堂々と語る方法』という本がある。
最初この本を書店で見た時、「変なハウツー本が出てる……」と少し軽蔑した目で見てしまったのだが、一方で、この本に対しての興味を抑えられなかったのも事実であった。
それで実際に手に取ってみたところ、めちゃくちゃ面白かった。
ぜんぜん、低俗な本ではなかったのである。今回は、この『読んでいない本について堂々と語る方法』について感想を書いていきたい。
『読んでいない本について堂々と語る方法』はどのような本か
本書の目次と構成
まず最初に、本書の目次を紹介しておこう。
Ⅰ未読の諸段階
ぜんぜん読んだことのない本/ざっと読んだ(流し読みをした)ことがある本/人から聞いたことがある本/読んだことはあるが忘れてしまった本
Ⅱどんな状況でコメントするのか
大勢の人の前で/教師の面前で/作家を前にして/愛する人の前で
Ⅲ心がまえ
気後れしない/自分の考え方を押しつける/本をでっちあげる/自分自身について語る
本書では基本的に、どのレベルで「読んでいない」本を、どのような場面・方法で語るのかを、ケース別に小説・評論等を紹介しつつ述べる構成をとっている。
(例えば第3章第3部「本をでっちあげる」では、夏目漱石の『吾輩は猫である』が取り上げられている)
本書は「反教養主義」の本ではない
目次と構成について紹介したところで、本書の内容について書いていこう。
この本が想定しているのは、タイトルの通り「読んでいない本について語る」 という場面である。
では、この本が「教養」というものを軽視しているのかと言うと、必ずしもそうではない。そもそも「本について語る」という営為自体が知的な営みであるように、筆者は知的な営みを軽視することは一切ない。
タイトルに嫌悪感を感じた人にこそ手に取ってほしい
その点で、本書のタイトルに対して「反知性的」だと感じた人には、むしろ手に取ってほしいと思うのである。結局「教養」は大事なのだと改めて感じさせる本でもある。
だがその一方で、本書は従来の「教養」あるいは「読書」の在り方について、一石を投じる本でもある。その点で、本書は読者に新しい読書像を開いてくれるはずである。
その理由は、以下で説明しよう。
「読んでいない本について堂々と語る方法」の実践
ここでは、筆者のいう「読んでいない本について堂々と語る方法」とは実際にはどのようなものかを、紹介しよう。
本の「位置関係」を把握する
たとえば筆者は、本の内容を知ることと同等に、本の位置関係を把握することが、その本を語るのに重要だと説く。
私はジョイスの『ユリシーズ 』を一度も読んだことはないし、今後もおそらく読むことはないだろう。したがってこの本の「内容」はほとんど知らないといっていい。
しかし位置関係はよく知っている。しかも本の内容というのも、じつはそれじたい本の位置関係とけっして無縁ではない。つまり私は、人との会話のなかで、ふつうに『ユリシーズ』について語ることができるのである。
なぜなら私はこの本を他の本との関係でかなり正確に位置づけることができるからだ。
私はこの作品が『オデュッセイア』の焼き直しであること、これが意識の流れという手法を用いていること、物語がダブリンでの一日を叙したものであることなどを知っている。
この理由から、私は大学の講義でもよく平気でジョイスに言及する。
この例からもわかるように、結局「ある読んだことのない本」を語るためには、他の本を読んでいる必要がある。
このような点で、「読んでいない本について堂々と語る」ためには、その本の著者に関する知識やその本の文学史上の位置づけなどの知識――すなわち教養が必要である。
しかし、文学史を学ぶというと難しく聞こえるが、作品の背景を語ることは、通俗的な作品について語るのであっても同じである。
たとえば、『鬼滅の刃』について語るのであれば、それが週刊少年ジャンプに連載されたマンガであることをまず紹介するだろう。
少年マンガを語るときに、それがジャンプか、サンデーか、マガジン(あるいはチャンピオン、ガンガン)かーーどの雑誌に連載され、他作品とどのような関係性があるのか、というようなことを語るのと同じようなものだと思う。
個人の中の価値観や、個人史と比較する
だが、「文学史の知識」や「作品の位置関係」がわかっていなかったら作品について一切語ることができないのかといえば、そうではない。
本書第2章第2節では、人類学者ローラ・ボハナンが、アフリカの部族ティヴ族の人々にシェイクスピアの『ハムレット』を読み聞かせた際の反応が紹介されている。
彼らは、まったく西洋の文化圏の人々とは違った反応を見せるのである。
冒頭の、ハムレットの死んだ父王の亡霊が登場する場面で、さっそく彼らはコメントをする。
それは死んだ首長(引用者註:父王)なんかじゃない。
それは魔術師が送ったサインだ。
ティヴ族の思想はある意味西洋よりも合理的で、彼らの文化に亡霊というものは存在しない。(魔術師は存在するが)
だから、このような反応を見せるのである。
このような、ティヴ族の『ハムレット』への読みというのは、実はシェイクスピア批評の中の一つの潮流である「ハムレットは幻覚を見ていたのだ」とする異説と同じところがあると筆者は説く。
ティヴ族の人々は『ハムレット』という作品を知らなかったが、作品の持つ無数の豊かさにアクセスすることができたのである。
この手法は、ティヴ族でない私たちも使うことができる。
自分の中の価値観や、自分の生きてきた人生と比較することで、ある本のいくつかの要素をつかみ取ってその本を雄弁に語ることができるのである。
何を感じたのかを重視してよい
このように、本書は所謂「教養」を礼賛しているというわけではない。
本書は必ずしもある本を一言一句違わないほど正確に通読する必要はないと説く点で、従来の教養に一石を投じている。
読んでいない本について気後れすることなしに話したければ、欠陥なき教養という重苦しいイメージから自分を開放すべきである。
(中略)
われわれには他人に向けた真実より、自分自身にとっての真実のほうが大事である。
後者は、教養人に見られたいという欲求ーーわれわれの内面を圧迫し、われわれが自分らしくあることを妨げる欲求ーーから解放された者だけが接近できるのである。
私たちが古典的作品を読むときに感じる気後れも、このような「欠陥なき教養」という観念が邪魔をしているのかもしれない。
だが、自分自身が感じた「主観的真実」を重視することこそ、古い「教養」から解放された人間に可能な境地なのである。そして、筆者はそのような境地を肯定する。
本書を読んで、何がよかったか
では、この本を読んで何が役に立ったかということについて、最後に私なりの感想を書いておこう。
読んだ本の感想を整理しやすくなった
たとえば私はこの書評ブログを書いているが、本書に書かれた「読んでいない本について堂々と語る」ための心構えというのは、書評を書くうえで非常に役に立っていることが多い。(一応誤解のないように断っておくが、私は最初から最後まで読んだ本しかこのブログでは紹介していない)
というのは、読んだ・読んでいないにかかわらず、この本は「本について語る方法」について述べた本だからである。
上に紹介したような「読んでいない本について語る方法」からもわかっていただけるだろうが、本書には本の感想を書くためのノウハウが詰まっている。
読んだ本を自分の中で整理しやすくなった
読んだ本の感想を整理しやすくなったというのは、読み終わった本を自分の中の「図書館」に整理しやすくなったことと同じである。
古典的作品を読むときは読む本の文学史上の立ち位置を最初に確認してから本を読むようになったし、また、さらにそれを自分の読書体験の中でどのように位置づけるかを考えるようになった。
そして、本に対する自分の主観的な読みも、誇っていいものだと思えるようになったからである。
創作にもインスピレーションを与えた
そして、本書が注目に値するのは、「読んでいない本について堂々と語る」ことを立派な創作活動と位置づけていることである。
たしかに、「読んでいない本について堂々と語る」というのは、ある意味創作活動である。
筆者は次のように書く。
自分の知らないことについて巧みに語るすべを心得ているということは、書物の世界を超えて活かされうることだからである。
言説をその対象から切り離し、自分自身について語るという、多くの作家たちが例を示してくれた能力を発揮できる者には、教養の総体が開かれているのである。
筆者ピエール・バイヤールが「読んでいない本について堂々と語る」ことを推奨するのは、それが創作活動の第一歩だからでもある。
あらゆる創作活動をしている人に、ぜひこのエッセンスをつかみ取ってもらいたいと思う。
おわりに
この本に書かれた読書に関する軽快なアドバイスは、すべての読書人に役に立つものではないかと思う。
「なるほど、こういう本の読み方もあるのか」という新しい発見があると思う。
なお、この本は先述の通り「本を最初から最後まで読まなくてもよい」とうスタンスなのだが、実はこの本は最初から最後まで読んだ方が良い。
ーー最後まで読んで、この本に仕掛けられたトリック(筆者はトリックではないと言うだろうが)があることに、気づくだろう。
この本は、そんな遊び心とウィットが満載の本である。
心からお薦めできる本である。
▼関連記事