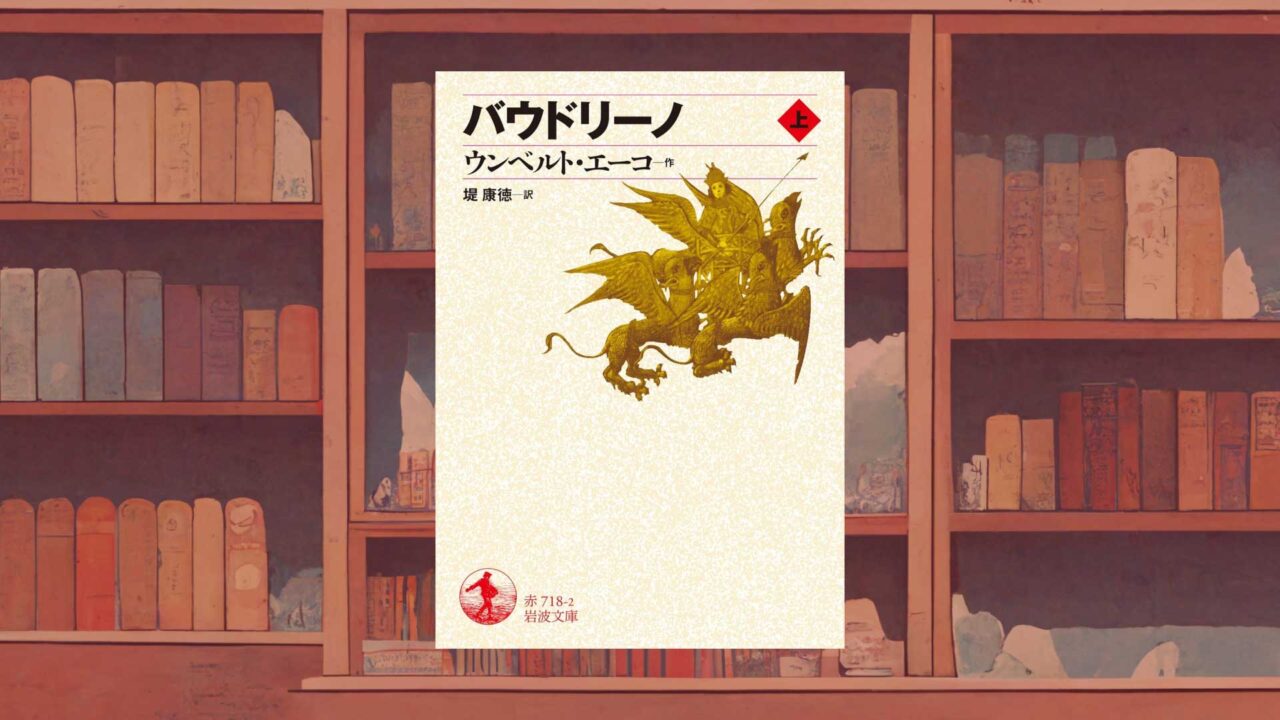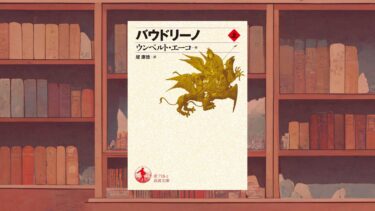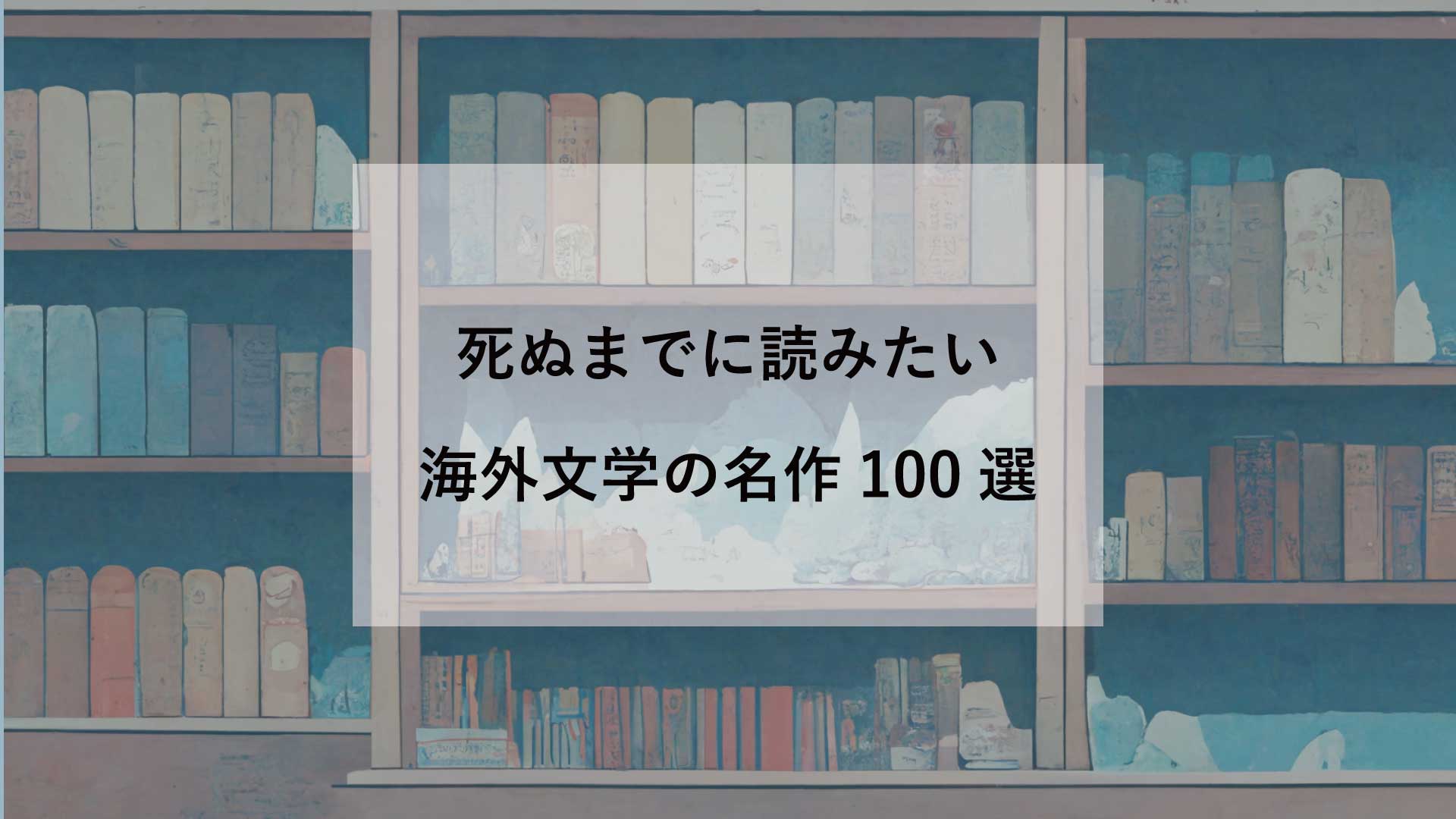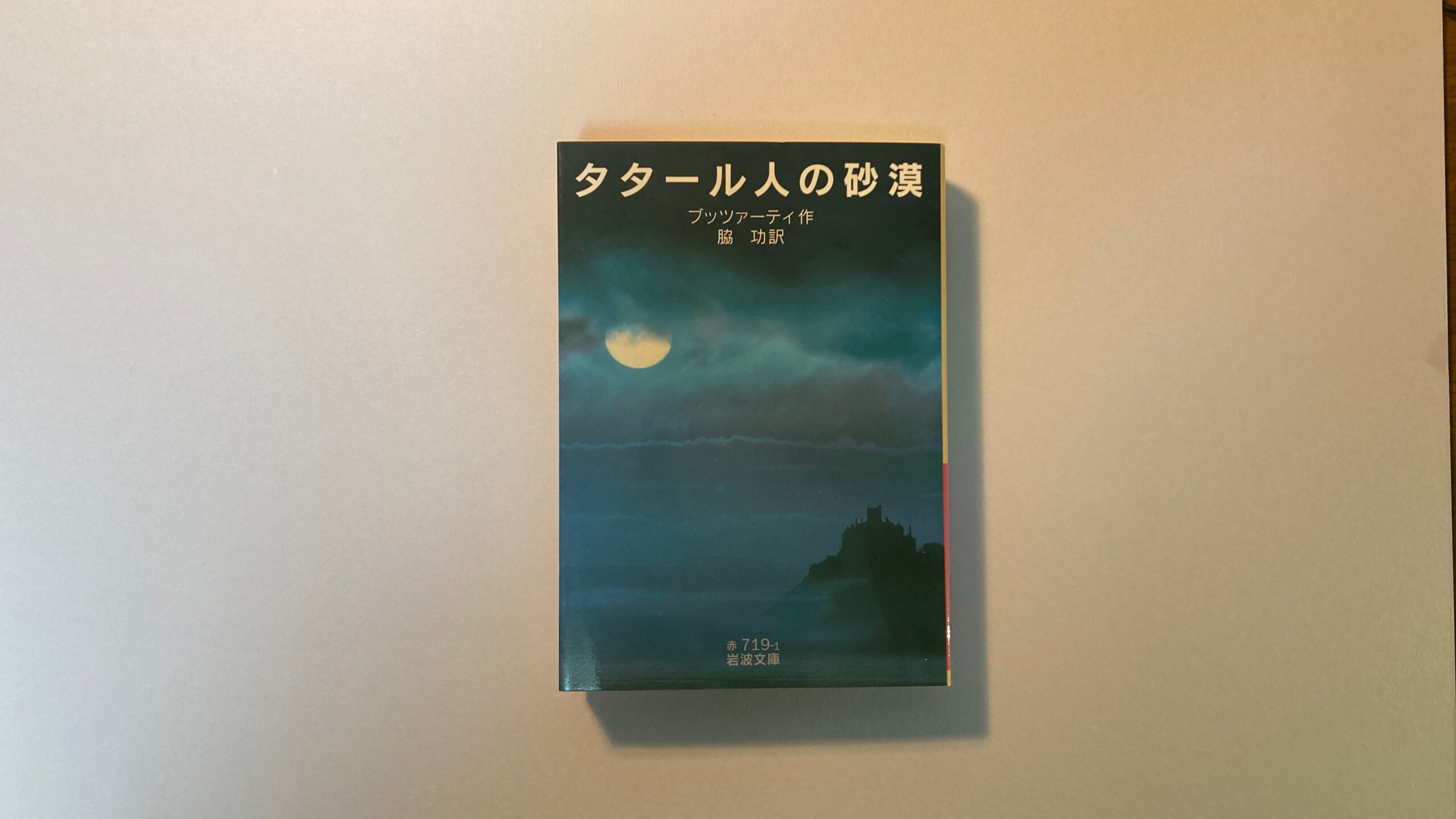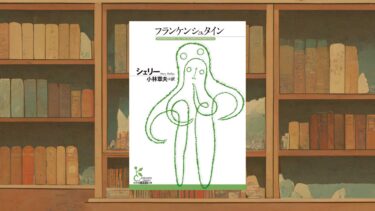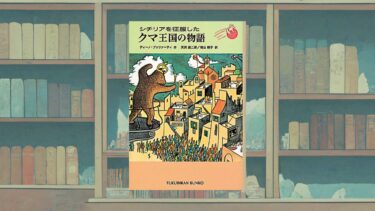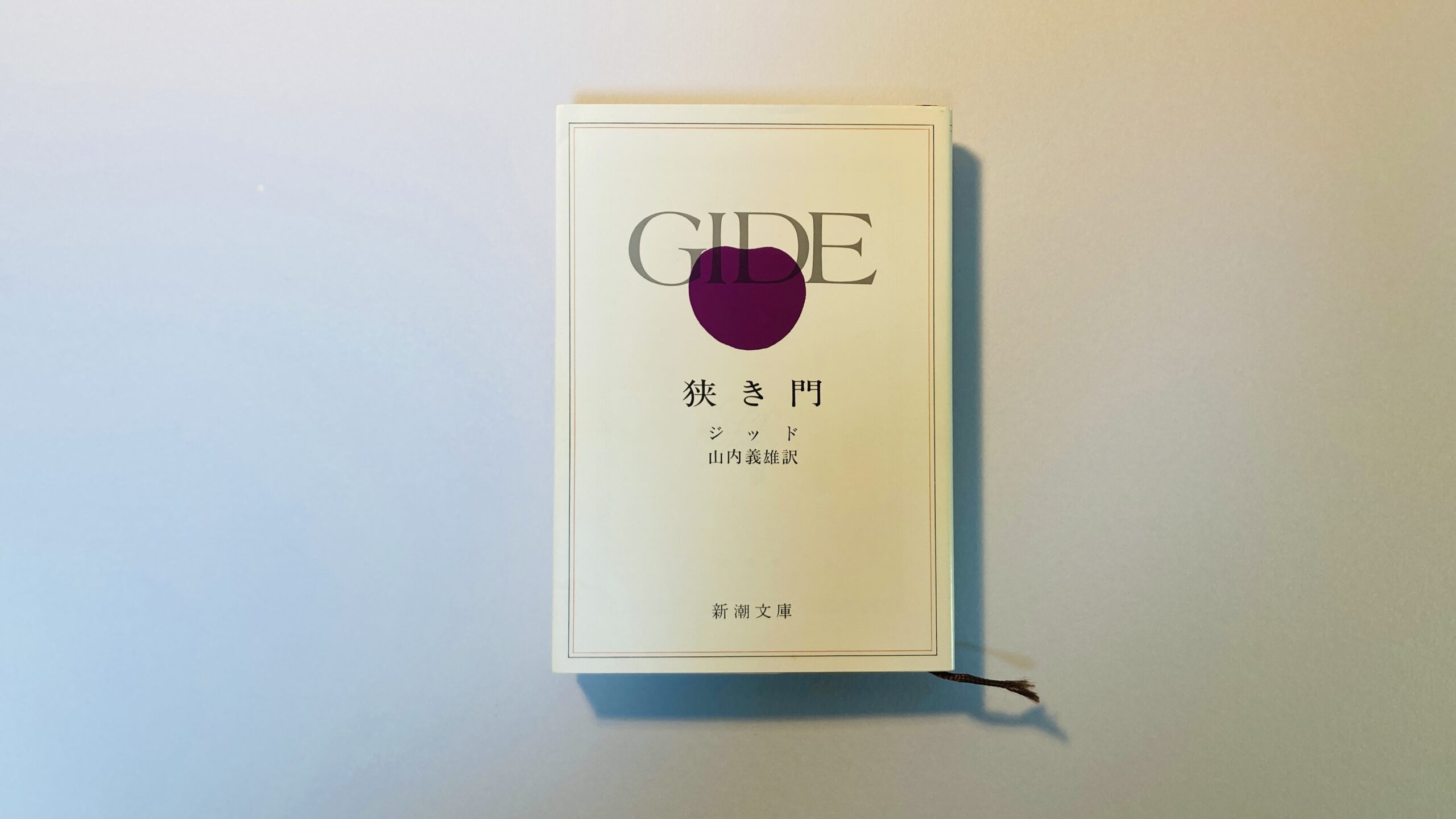別に私は小説家になるために努力をしているわけではないが、「こんな小説を書いてみたい」という嫉妬のような感情を、小説を読んでから抱くことがある。
個人的に、一番「こんな小説を書いてみたい」と思った小説は、ウンベルト・エーコの『バウドリーノ』という小説である。
ウンベルト・エーコといえば、代表作である長編小説『薔薇の名前』やジャン=クロード・カリエールとの共著『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』で知られる知の巨人である。彼は小説家デビューする以前、すでに世界的に著名な記号論理学者だったが、50歳を超えて小説を書き始めた。
なぜエーコが小説を書き始めたのかというと、学術論文では表せないことを小説で表せると考えたからだという。だからエーコの小説には、何か彼が伝えたかったものがあるのであり、『バウドリーノ』という小説も例外ではないだろう。
私は、『バウドリーノ』という小説は「歴史小説とは何か」という問いについての一つの答えを示した作品だと思う。今回はこの小説の面白さ、素晴らしさについて書いていきたい。
エーコ『バウドリーノ』あらすじ
はじめに紹介すると、『バウドリーノ』という作品の舞台は中世ヨーロッパである。
あまり世界史に馴染みのない人にとっては、読み始めるのをためらってしまうかもしれない。この作品を読み始めるハードルをできるだけ低くするため、初めにこの小説の舞台となる歴史的背景を紹介したい。
『バウドリーノ』中に登場する世界史用語
まずはじめに、この物語の主人公はタイトルの通りバウドリーノという人物であるが、バウドリーノは虚構の人物である。
フリードリヒ1世…「バルバロッサ」(赤髭王)の異名を取った神聖ローマ皇帝(1122 – 1190)。イタリア政策と呼ばれる、イタリアへの南下政策をとり、ローマ教皇と対立。レニャーノの戦いで教皇派(ロンバルディア同盟)に敗れてからは、内政に注力する。第3回十字軍の総司令として出征し戦果を挙げるが、出征先のキリキアで溺死という最期を迎える。
ニケタス・コニアテス…中世の東ローマ帝国のもっとも優れた歴史家とされる。物語は1204年、第4回十字軍によりコンスタンティノープル(現在のイスタンブール)が陥落し、ニケタスがバウドリーノに救出されるところから始まり、バウドリーノがニケタスに自らの半生を語るという形式をとる。史実ではヴェネツィア商人が彼を町の外に脱出させたとされる。
司祭ヨハネ伝説…プレスター・ジョン伝説とも。12世紀のヨーロッパでは、アジアまたはアフリカにキリスト教国の国王がいると信じられていた。この伝説をバウドリーノが物語中盤のキーとなる。
物語中には、シャルルマーニュや聖遺物の話など、現代日本ではなじみのない用語も飛び交うが、適宜Wikipediaなどで調べると物語がより楽しめるのではないかと思う。
『バウドリーノ』あらすじ
次にあらすじの本題に入っていきたい。この小説は、神聖ローマ皇帝フリードリヒ・バルバロッサの養子となった農民の子、バウドリーノの数奇な人生を描く。
物語は1204年、第4回十字軍によってコンスタンティノープルが陥落する場面から始まり、ビザンツ帝国の歴史家ニケタスは、略奪から逃れる途中バウドリーノという男に助けらる。そしてバウドリーノは、自らの半生をニケタスに語り始める。
「今なら私にも語るべき歴史があると言えましょうが、私の過去について書いたものすべてを失くしてしまったばかりか、思い出そうとすると考えが混乱するのです。……今日私の身の上に起きたことを、誰かに話さずにはいられません、さもなければ気が狂ってしまう」
「私は人をひとり殺しました。それは、十五年前に、私の養父、王の中の王、皇帝フリードリヒを殺した男なのです」
ニケタスは、バウドリーノの告白に「フリードリヒはキリキアで溺死したはずだが?」と返す。だが、バウドリーノによると、フリードリヒは殺されたのだというーー。
しかし、物語はバウドリーノが語る彼の幼少時に移る(フリードリヒの死の真相は物語の最終盤まで楽しみにしていてほしい。どんでん返しもある)。
バウドリーノが語る彼の半生は、こうだ。
バウドリーノは、イタリア北部の貧しい農民の子として生まれた。幼少期から言語習得の天才的な才能を持ち、聞いただけで新しい言語をすぐに覚えることができました。この才能が縁で、神聖ローマ皇帝フリードリヒ・バルバロッサに見出され、彼の養子となる。
物語前半では、彼は学問のためにパリに留学する(ちなみにパリに留学するのは、いわゆるエディプスコンプレックス、つまりバウドリーノが皇妃・ベアトリクスに恋をしてしまったからというのが大きな理由の一つである)。そこで聖ヨハネの王国という伝説を知ることになり、青年バウドリーノの冒険が始まる。
そして、第3回十字軍に参加することになりーー。
『バウドリーノ』の何が凄いのか
『バウドリーノ』という小説は、一度読んだだけでは理解できない部分も多い緻密な小説で、簡潔に紹介するのは難しいが、簡単なあらすじは以上のようなものになると思う。
ここからは、『バウドリーノ』という作品がいかに凄いのかということに書いていきたい。
私が思うに、『バウドリーノ』という小説は、「歴史小説は歴史学との対立をどのように乗り越えるべきなのか」ということを、小説でもって明らかにした小説だと思うからである。
歴史と歴史小説のあいだ
歴史学と歴史小説には、しばしば緊張関係がある。
2024年の大河ドラマ『光る君へ』はドラマとして非常に面白かったが、そこで描かれたことは史実をモチーフにしているが、当然史実とはいえない。このドラマで時代考証を担った倉本一宏氏も、著書で以下のように述べている。
「ドラマのストーリー性が独り歩きして、紫式部と道長が実際にもドラマで描かれるような人物であったと誤解されるのは、如何なものかと思う。」(倉本一宏『紫式部と藤原道長』 (講談社現代新書) )
さらには「貧乏学者の娘と、右大臣家の御曹司とが、幼い頃に知り合いだったということは、現実的にはあり得ないことである」とも。
しかしかといって、たとえば紫式部と藤原道長のあいだにロマンスというものがあった可能性は「ほぼ0%」といえるが「完全に0%」であることを証明することは、悪魔の証明である。
そういった可能性を、歴史学者が学術論文としてそのようなことを主張するのは不可能であるし、たとえ一般人であっても「ありえないはずのことだが、完全に0%であることを証明できない」説を支持するのは歴史修正主義的である。だが、そういった説を小説として発表することは、あくまで小説である限り問題ない。ここに歴史小説というものが生まれる余地があるのだ。
もちろん、それはあくまで「小説として」であることには注意が必要である。
『バウドリーノ』という小説は、まさに「史実ではないが、史実としてあったのかもしれないこと」を描いている。
一方『バウドリーノ』が、歴史学者から「史実への誤解を招く小説である」と思われている可能性は、(私がイタリア人ではないのでなんともいえないところではあるが)ほぼないのではないかと思う。
それはこの小説のギミックとして、バウドリーノ自身も嘘つきであるということが理由の一つだろう。物語序盤で、こうニケタスが喝破しているように。
「あなたは、まるでクレタ島の嘘つきだ。自分は札付きの嘘つきだと私に言っておきながら、自分を信じろと私に要求する。あなたは自らの告白によって、自分が誰か、もはやわからなくなっている。おそれくそれはまさに、あなたがあまりにも多くの嘘を、あなた自身にもついてきたからなのです」(P80)
『バウドリーノ』は歴史を題材にした小説であるが、歴史学との対立を避けることに徹底的に成功しているのである。
だからある意味この小説は信頼できない語り手が語っているという点で「歴史小説」とはいえないのかもしれないが、だからこそ、この小説は歴史学と対立することを避けることに成功しているのだ。
歴史修正主義に立ち向かう
重ねて述べるように、歴史上、学説としてはあり得ないが「0%であることを証明できない」というものを、小説として楽しむのは構わない。
しかし、それを利用した歴史修正主義に対しては、対抗しないといけない。エーコが評論『歴史が後ずさりする時』でこう述べているように。
「『偉大なる嘘』や、それが支え続ける憎しみに立ち向かうために、語り続けることには意義があるのだ」(ウンベルト・エーコ『歴史が後ずさりするとき』407ページ)
おわりに
ここまでウンベルト・エーコの『バウドリーノ』という小説について述べてきた。この小説の素晴らしさが伝わったかはいまいち自信がないが、私が『バウドリーノ』という小説の最も素晴らしいと思う点は重ねて書いているように、歴史小説にメタフィクションを導入し、「歴史学と歴史小説の対立」という問題に一つの答えを出していると思うからである。
興味を持った方は、岩波文庫で読むことができるので、ぜひ一度読んでみてほしい。
上下巻と長いので物語は多少冗長に思うところもあるかもしれないが、訳者があとがきで
バウドリーノの語る数奇な生涯は、史実と伝説と空想が織りあわされて奇想天外な紋様をつむぎだすタペストリーさながらであり、作者が想像力の翼を自由にはばたかせて、楽しみながら物語を書いているのが読者にも伝わってくる。
と書かれているように、ウンベルト・エーコ自身が楽しんで書いている様子が伝わる、まさに筆の乗った小説である。
そして物語最終盤のカタルシスと読後感は、この長さの長編小説を読まないと味わうことができないものである。だから、全2巻であることを理由に敬遠することなく、物語の長さも楽しんでもらいたい小説である。
ところで筆者は記事執筆時点ではまだ読んでいないが、エーコには『ウンベルト・エーコの小説講座』という本がある。この本を読めば、『バウドリーノ』のような本が書けるのかもしれない。
海外文学の良いところは、他国の歴史や文化を感じることができるところだ。日本の文学も好きだけれど、それぞれ違った良さがある。海外文学を読んでいるうちに、主要な海外文学を死ぬまでに読んでみたいという気持ちになってきてきた。だが、「海外文[…]
ベルルスコーニが死んだ。ベルルスコーニといえば、実業家として特にテレビ局などのメディアを掌中に収めた「メディア王」であり、汚職や脱税など数多くの不正疑惑で捜査を受けつつも、合計9年以上イタリアの首相の座にあった人間である。アメリカのトランプ[…]
人生とは、有限で、老いとともに色々な可能性を失っていくもので、短く、たいていの人は何かを成し遂げることさえできずに終幕を迎えるものである。そのようなことをテーマにした世界文学の名作として、イタリアの作家ディーノ・ブッツァーティの『タ[…]